登山と自転車の補給食を考える会です。
私が補給食に求める要素は以下の通りです。
①脂肪分が少ない … 消化が遅くエネルギーになりにくいし、もたれるので。
②軽く、かさばらない
③食べていて飽きない
④そこまで高くない
要するに、安価に美味しく炭水化物・糖質が取れる食べ物を探す会です。
行きましょう、
・大福
本命です。トップバリュだと200円以下で5個入りの大福が買えますが、一袋で800kcalくらい摂れる優秀なアイテム。水分があるので口が乾かないのがGood。
100gあたり246g(糖質27.3g/たんぱく質4.4g/脂質0.6g)

・グミ
私はハリボーのグレープフルーツ味が好きです。
100gあたり343kcal(炭水化物77.4g/脂質0.1g/たんぱく質6.9g)
脂質がかなり少ないので、いい感じです。

・濡れせんべい
普通のせんべいは口が乾くので、私は濡れせんべいの方が好きです。
100gあたり301kcal(炭水化物70g/脂質0.4g/たんぱく質4.3g)

・羊羹
もらいものをそのまま山へ持っていくことが多いです。
日持ちするのでGood。黒糖の甘みが優しい。
100gあたり292kcal(糖質68g/脂質0g/たんぱく質4g)
黒糖も持っていきましたが、カリウムが多いのかトイレが近くなる気がします。

・いかフライ
みんな大好きなとりのいかフライ。
5枚で大体55gくらいでした。脂質多いですが調達難易度の低さと重量当たりのカロリーが良いバランス。余ったらそのままおつまみにできますからね。
110gあたり524kcal(炭水化物56.8g/脂質28.4g/たんぱく質10.4g)

定番の非常食。昔はもっとパサパサしてたように思うのですが、最近食べやすい気がします。改めてカロリーを見ると脂質ちょっと多いですね。
80gあたり400kcal(炭水化物43.4g/脂質22.2g/たんぱく質8.2g)

・カステラ
かさばりますが、意外と低脂質でハイカロリー。
100gあたり314kcal(炭水化物61.8g/脂質5g/たんぱく質7.1g)

時間とお湯を沸かせる環境があればこれ。
100gあたり366kcal(炭水化物82.7g/脂質1.1g/たんぱく質6.3g)

・水あめ
水に溶かさないと飲めないですが、最強の低脂質 補給食です。
私が自転車に乗るときは大抵これメインです。
100gあたり384kcal(炭水化物95.5g、水分4.5g)

以上、いかがでしたでしょうか。
艇脂質にこだわるとこういう形になってくるのかなと思います。
皆さんのおすすめがあれば教えてください。
![サントリー ウイスキー 角瓶 [日本 700ml ] サントリー ウイスキー 角瓶 [日本 700ml ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41QewqQQyjL._SL500_.jpg)
![サントリー バーボン ウイスキー 白角 [日本 700ml ] サントリー バーボン ウイスキー 白角 [日本 700ml ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41v9OFYSAjL._SL500_.jpg)
![角瓶 サントリー 特撰白角水割 [ ウイスキー 日本 250mlx24本 ] 角瓶 サントリー 特撰白角水割 [ ウイスキー 日本 250mlx24本 ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Su+-0iIQL._SL500_.jpg)


![デュワーズ ジャパニーズスムース 8年 [ ウイスキー イギリス 700ml ] デュワーズ ジャパニーズスムース 8年 [ ウイスキー イギリス 700ml ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41CAxqb2YVL._SL500_.jpg)



























 山梨市街が一望できるのがいいですね。
山梨市街が一望できるのがいいですね。

 昔、山梨から登った人がいたんだろうなぁと思いますが、近いようで遠い、神聖なこの山がとても好きになりました。標高3000m近い山から市街地を眺められることはなかなかないです。
昔、山梨から登った人がいたんだろうなぁと思いますが、近いようで遠い、神聖なこの山がとても好きになりました。標高3000m近い山から市街地を眺められることはなかなかないです。







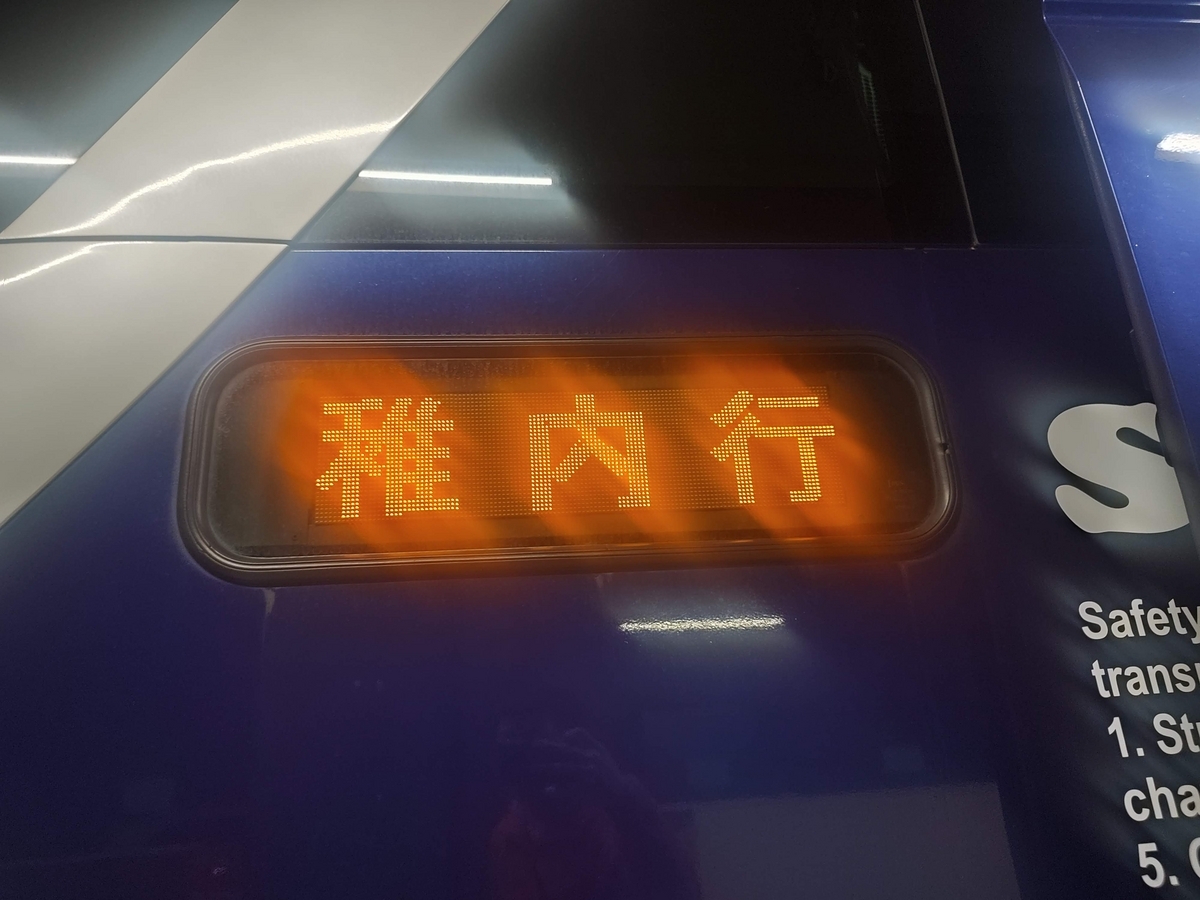























































































 これは7月頃の庭です。奥の壁側と右手前、それと左奥の木が生えているところを山に見立て、その間を谷に見立てることにしました。
これは7月頃の庭です。奥の壁側と右手前、それと左奥の木が生えているところを山に見立て、その間を谷に見立てることにしました。







 この頃は
この頃は











































































